相続対策でも使える「契約者代理」
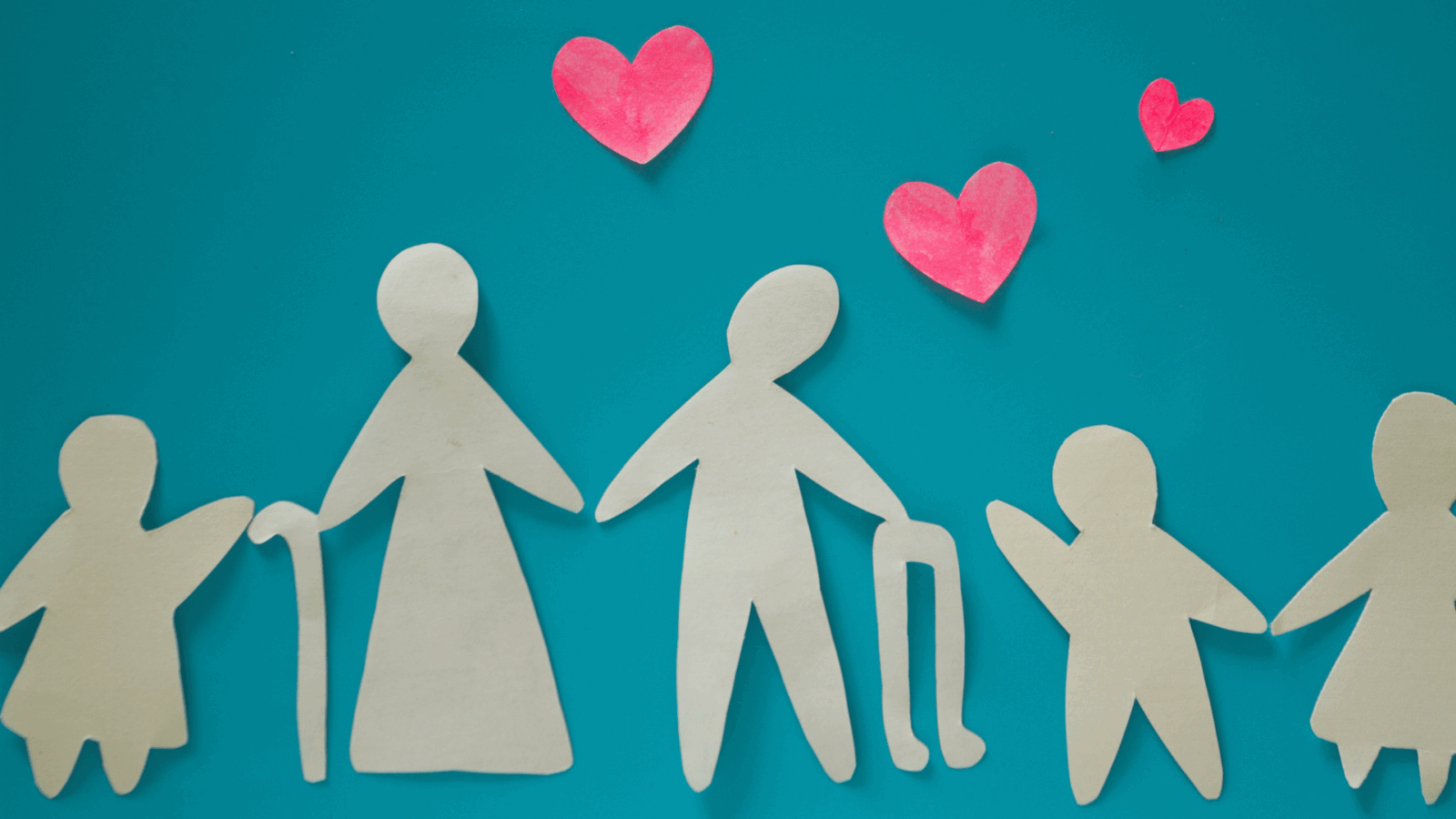
相続対策というと、不動産や生前贈与、遺言書などがまずは思い浮かぶかもしれません。
また生命保険も相続対策としてしばしば活用されています。
その保険に関する制度の中に「契約者代理」という制度があります。
今回はその契約者代理が相続対策でも活用できるということについて解説していきます。

「契約者代理」とは
「契約者代理」制度とは、保険契約をしている人(契約者)に代わって、あらかじめ指定された人が代理人となり、契約の内容確認や変更、解約などの手続きをすることができる制度です。
契約者が認知症などになり意思表示が困難になった際や、高齢になり手続きがたいへんになった際などに、代理で手続きをすることができます。
高齢の親が子など信頼できる家族を契約者代理人に指定しておくことで、スムーズな手続きが可能となります。
親の意思を尊重しつつ、手続きの負担を軽くすることができ、安心につながるかもしれません。
相続対策での3つの活用法
活用法① 保険契約の見直し・変更がしやすくなる
保険金の受取人や保険金額など契約内容の変更を、契約者に代わって手続きできるため、相続対策に合わせて柔軟に対応することができます。
例えば、高齢の父が若い頃に加入していた生命保険があったものの、保障額が小さく相続税の対策にもなっていない契約内容だった場合に、子が契約者代理人として変更手続きをして、死亡保険金の非課税枠を活かせる保険に切り替えます。
父の意思を確認することがもちろん大切ですが、「契約者=父・被保険者=父・受取人=子」という契約に変更することで、相続時の「500万円×法定相続人の数」という非課税枠を活用できるようになりました。
活用法② 生前贈与型の保険契約への対応
例えば、祖父母が契約者となって孫の学資保険を契約するようなケースは、「孫への生前贈与」のようなものとして利用されます。
そうした際に、子(孫の親)が契約者代理となって、保険の管理や給付金請求などの手続きをすることで、祖父母の負担を減らすことができます。
活用法③ 認知症への対応
相続対策を進める上でリスクとなるのが健康問題、特に認知症です。認知症になり、意思表示が困難になると保険の管理もできなくなってしまいます。
認知症になってしまった後には、法定後見制度を使うことになりますが、保険に関しては事前に契約者代理制度を利用していれば、問題なく保険の管理ができます。
例えば、高齢の親の医療保険やがん保険の給付金請求や、保険の見直し、不要になった保険の解約などを、契約者代理人になっている子が、手続きすることができることになります。
また、個人年金保険がある場合に、老後資金の管理を契約者代理人がすることもできそうです。
契約者代理の注意点
・契約者本人の意思を確認してから手続きをする
・委任状や本人確認書類など必要書類の準備をしっかりしておく
・保険会社によってルールが異なるので、事前に確認する

まとめ
保険の契約者代理制度は、うまく利用すると相続対策のさまざまな場面で役立ちます。
そして、なにより家族の信頼が大切です。
高齢の親と子、孫が一緒に考えていくことが、円満な相続につながるのではないでしょうか。


