老朽アパートの相続 持つか売るか、判断のポイント
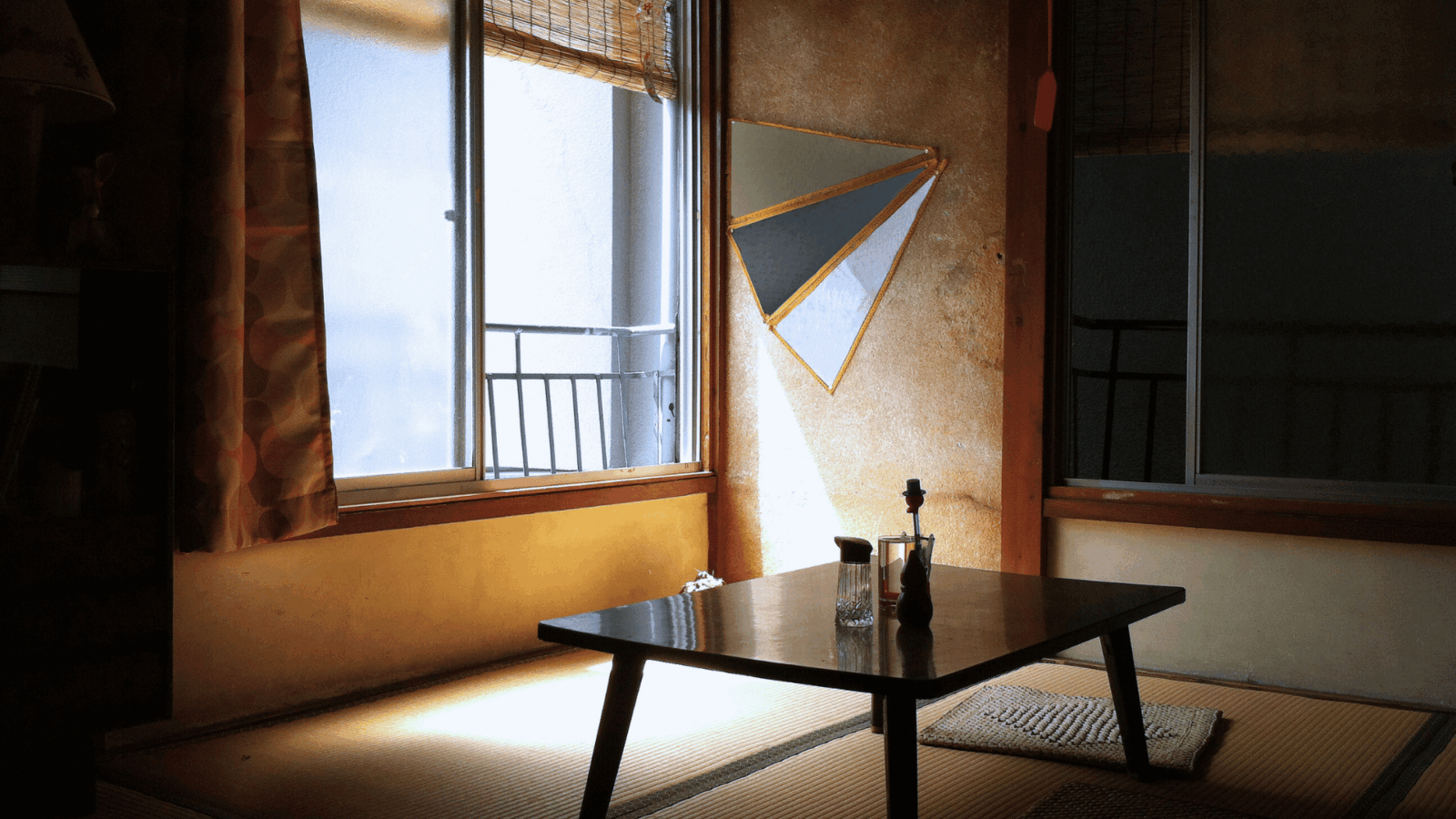
「親が残してくれた築40年のアパート。空室もあるけれど、毎月一定の家賃は入ってくる。修繕費もかかりそうだけど、このままにしておいていいのだろうか・・。」
古いアパートを相続すると、「持つか」「売るか」で悩む方が少なくありません。
古いとはいえ、家賃収入がある。土地としての資産価値もあるかもしれない。でも、実際に賃貸経営を引き継ぐのは、自分にとって荷が重い……。
相続された老朽アパートは、親の思いと、現実の経営判断が交錯する、悩ましい存在です。
そして、問題を先送りにしているうちに、建物はさらに老朽化し、収支は悪化し、いざというときに「どうにもできない」状態になってしまうこともあります。
このコラムでは、そんな悩める相続人の方に向けて、老朽アパートの相続での課題、「持つか」「売るか」あるいは他の選択肢を判断するポイント、必要な知識などについて、やさしくわかりやすく解説します。

老朽アパートの相続で直面する6つの課題
築30年、40年を超えるようなアパートには、それなりの「課題」があります。
建物そのものが古くなっているだけでなく、時代によって経営のあり方も変わってきています。
以下は、実際に老朽アパートを相続した際に直面する6つの課題です。
修繕費用の増大
老朽化した建物は、日常的なメンテナンスでは対応しきれないことが多々あります。
外壁の補修、給排水設備の取り替え、防水工事、屋根の修理など、数百万円単位の出費が発生することも珍しくありません。
家賃下落と空室リスク
古い物件は、設備の古さや見た目の印象から、家賃を下げないと借り手がつきにくい状況になります。
借り手がつかず空室が増えると収支が悪化し、赤字運営に陥るリスクが高まります。
「大家」業のハードル
親の世代は自分で管理や修繕をしていたとしても、子の世代にとっては未知の世界です。
「家賃滞納への対応ってどうするの?」「入居者クレームは誰が対応するの?」と、賃貸経営のハードルを高く感じる方も少なくありません。
相続人の間の共有
アパートが複数の相続人で共有となった場合はやっかいです。
相続人の意見が合わないと、「修繕の判断がまとまらない」「売却の話がまとまらない」「一人が住んでしまって他の人が口を出せない」といったトラブルも起こります。
税金や管理費などの負担
相続税を支払ったあと、手元に現金が残っていないのに、固定資産税や管理費、修繕費が発生し続け、家賃収入を超えてしまうという「逆ザヤ状態」になることもあります。
心理的なプレッシャー
「親が大事にしていた不動産を、自分が手放していいのか」という罪悪感が生まれるかもしれません。
あるいは「売却したら親族から責められそう」といった周囲の目も気になり、判断を鈍らせる要因となることが考えられます。
このような「課題」に直面することから、「持つか」「売るか」あるいは他の手があるのか、検討することが必要となってきます。
「持ち続ける」判断のリアル
「せっかく親が残してくれたアパートだから、できれば自分が引き継いで運営したい」
そんな気持ちを持つ方も多いと思います。実際、「持つ」という選択肢には、家賃収入といういわば安定した「不労所得」を継続して得られる可能性があります。
また、賃貸不動産には相続税対策や将来的な資産形成の面でも一定のメリットがあります。
ただし、「持ち続ける」という選択には、それ相応の覚悟と準備が必要です。
ここでは、現実的なメリットとリスクを整理してみます。
持ち続けるメリット
✔️ 家賃収入
入居者がいれば、毎月安定的に家賃収入が得られます。
アパートにローンが残っていなければ、固定資産税や管理費を差し引いても手元に収益が残るケースもあるでしょう。
老後の生活資金やお子さんの教育費などに充てることができるのは、大きな魅力となります。
✔️ 資産として将来の売却
「今すぐには売らず、将来状況が整ったら売る」という柔軟な選択肢も持てます。
地価が安定している地域や、再開発の可能性があるエリアであれば、売却益がでるかもしれません。
✔️ 税負担の軽減も
賃貸不動産は、「貸付事業用宅地」として小規模宅地等の特例が適用され、相続税評価額が大きく下がる場合があります。
また、賃貸経営での経費を計上することで所得税の負担を軽減できる場合もあるので、うまく活用することができればメリットは大きいといえます。
持ち続けるリストと注意点
⚠️ 修繕・設備更新のコスト
築年数の古いアパートでは、配管・屋根・外壁・電気系統などの経年劣化によるトラブルが多発します。
入居者募集のためにリフォームをするとしても、1室100万円以上かかるケースもあります。数室まとまって空室になった場合、一気に大きな出費が発生する可能性があります。
⚠️ 空室率の上昇と収支の悪化
一般的に「築古」+「駅から遠い」+「設備が古い」物件ほど、入居者は減る傾向にあります。
空室が多くなって収支がマイナスに転じることも想定されます。さらに、空室率の悪化は将来の売却価格にも悪影響を与えることになります。
⚠️ 管理負担の重さ
自主管理を続ける場合には、クレーム対応・修繕手配・契約管理などに相当な労力が必要です。
管理会社に委託する場合も、一定の費用がかかりますし、良い業者を見つけられるかどうか、信頼関係の構築も鍵となります。
⚠️ 相続人の間での意見の食い違い
兄弟姉妹で共有して持ち続ける場合、「誰が管理するか」「収益をどう分けるか」「修繕費の負担をどうするか」などで意見がまとまりづらいことが多いようです。
明確なルールがないと、争いの火種になりやすいので要注意です。
「持ち続ける」という判断には、「今の状態で黒字かどうか」だけでなく、将来を見据えた「大家としての責任」を果たせるかを考えることも重要です。
「売却する」判断のリアル
「とにかく不安が多すぎる。家賃収入よりも、現金を手にしたほうが安心できる」
「相続人どうしの揉め事になるくらいなら、売ってきれいに分けたい」
こうした理由から、早めに売却して現金化するという判断もあります。
「売却」のメリットと注意点を見ていきます。
売却のメリット
✔️ 資産を分割しやすくする
相続した不動産は、現金とは違って分けづらく、運用の手間もかかります。
売却して現金化することでスッキリと分配も可能になります。分けやすくすることで、相続人の間のトラブルも回避できるかもしれません。
高齢の親族や不動産に詳しくない方が相続する場合にも有効と言えます。
✔️ 手間から解放される
賃貸経営に不安がある方、遠方に住んでいる方などにとっては、物件を持ち続けることそのものがストレスになります。
売却することで、管理や修繕、トラブル対応の負担などから解放されます。
✔️ 高値売却の可能性
市場環境が良い場合には、想定よりも高額で売却することができるかもしれません。
都心や再開発エリアでは、築古物件でも土地目当ての購入ニーズがあるため、意外な高値がつくケースもあります。
特に最近は、インフレ懸念の高まりによる不動産投資ニーズが一定数あるため、売却の好機との見方もあるようです。
売却のリスクと注意点
⚠️ 想定外の安さも
立地や管理状況が悪いと、「解体前提」でしか売れず、安く買いたたかれることもあります。
老朽アパートは建物にはほぼ価値がないと見なされるケースが多いので、「土地」としての評価に依存することになり、売却価格が思っていたよりもかなり低くなることがあります。
⚠️ 譲渡所得税
売却益が出た場合には、譲渡所得に対して20%程度の税金が発生します。
(取得費や特別控除などで減額される場合もあります。)
売却前に、税理士などに試算してもらうのが安心です。
譲渡所得 = 譲渡価格 − ( 取得費 + 譲渡費用 )
税額 = (譲渡所得 − 特別控除 ) × 税率
* 譲渡価格:土地・建物の売却代金、固定資産税等の精算金
* 取得費:土地・建物の取得費用から減価償却費を引いた金額、取得価格がわからない場合は譲渡価格の5%
* 税率:約20%(老朽アパートは長期(5年超の所有)になるとの想定)
⚠️ 売却に時間がかかることも
築古物件は、融資がつきにくく、個人投資家の投資対象になりにくいため、なかなか買い手が見つからないことがあります。
売却まで数ヵ月〜1年以上かかるケースもあり、売却のタイミングの見極めも重要となります。
「売却」は、そのアパートに関わる責任を完全に手放す選択です。
スッキリとした整理ができる一方で、価格やタイミングの判断を誤るとむしろ損失が大きくなることもあるため、慎重な判断が大切です。
【「持つ」と「売る」の比較】
| 比較項目 | 持ち続ける | 売却する |
| 家賃収入 | 継続的に得られる | なし |
| 手間 | 管理・修繕の負担 | なし |
| 税務 | 所得税・相続税軽減も | 譲渡所得税の負担も |
| 現金化 | なし | 可能 |
| 感情面 | 親の思いを継承 | 心苦しさが残ることも |
「持つ」「売る」以外の選択肢
相続した老朽アパートを「持ち続けるか」「売ってしまうか」。
この2択で悩んでいる方は多いですが、実はその中間や、さらに柔軟な選択肢も存在します。
ここでは、現実的な「第三の道」として検討できる4つの対策を解説します。
建て替え
老朽化が進み、修繕だけでは限界が見えてきた場合、思い切って建て替えるという選択もあります。
新築にすることで、入居ニーズが高まり、賃料単価も上がりやすくなります。
メリット
⚫︎ より長期の安定収入が見込める
⚫︎ 耐震性や設備が向上し、入居者を集めやすい
⚫︎ 不動産として資産価値の向上が期待できる
デメリット
⚫︎ 建て替え資金(数千万円単位)が必要
⚫︎ 融資の審査に通らない可能性も
⚫︎ 建て替え中は家賃収入がゼロとなる
また、再建築が制限されている「再建築不可物件」や、敷地が狭小な場合は、そもそも建て替えができないケースもあります。
解体して更地に
「アパートとしては限界。でも売りたくはない」
そんな方には、建物を解体して更地として活用するという選択肢があります。
たとえば、駐車場、貸し農園、資材置場、自販機事業などです。
メリット
⚫︎ 活用時の初期費用が安く済む
⚫︎ 維持管理の手間が減る
⚫︎ 土地を持ち続けて活用できる
デメリット
⚫︎ 解体費用がかかる(数百万円)
⚫︎ 固定資産税の負担が重くなる(住宅地の6分の1特例がなくなる)
収益性は限定的ですが、「いったん更地にしてからどうするか考える」という「一時避難的な使い方」としても有効な方法と言えます。
プロに任せる
「自分で管理や経営をしたくない」という方には、サブリース契約や、都市部であれば等価交換による再開発も選択肢になります。
サブリースとは
不動産会社が物件を一括で借り上げ、オーナーには固定の賃料を支払い続ける契約方式です。
賃貸経営の運営の手間は減りますが、サブリース契約は、解約が難しいなどのリスクもあるので注意が必要です。
等価交換とは
土地を開発業者に提供し、代わりに新築物件の一部を取得するしくみです。
再開発地域でよく見られる方式ですが、機会は多くはありません。
メリット
⚫︎ 自ら経営しなくてよい
⚫︎ 管理の手間や空室リスクを減らせる
デメリット
⚫︎ サブリースは契約に注意が必要
⚫︎ 等価交換は機会が少なく、条件も厳しいことが多いので利用できるケース自体が少ない
不動産小口化商品への組み替え
アパートを売却した資金を使って、不動産小口化商品(不動産ファンドなど)に再投資するという選択肢もあります。
「不動産を持つことによる収益性と、手間のなさ」を両立することが可能です。
メリット
⚫︎ 自ら経営しなくてよい
⚫︎ 収益は定期的に分配される
⚫︎ 相続対策としても活用できる
デメリット
⚫︎ 元本保証はない(価格変動リスクがある)
⚫︎ 利回りは現状、それほど高くない
⚫︎ 出資金を動かせない期間がある
最近では、相続対策としてこのような仕組みに資産を組み替えるケースも増えています。
→関連コラム「『不動産小口化商品』の相続リスク」
「持つ」「売る」以外にも、「建て替える」「更地にする」「プロに任せる」「組み替える」など、選択肢は思ったより多くあります。
「自分の状況に合うかどうか」という視点で選ぶことが大切です。
判断の7つのポイント
老朽アパートを相続して、「持つ」「売る」「その他の活用」と、さまざまな選択肢を見てきました。
でも、結局どれが正解かわからない。
そんなときは、次の7つの視点から、自分の状況に照らして判断してみるのはいかがでしょうか。
ポイント① 年間の収支は黒字か
まずは、家賃収入から経費(固定資産税・管理費・修繕積立・保険など)を差し引いた「手残り」がプラスかどうか」を確認しましょう。
✔️ プラス → 「持つ」も視野に入る
⚠️ マイナス → 何か手を打たないと、収益がなくむしろ費用が持ち出しになる「負動産」に
見かけ上は黒字でも、「今後の修繕費が控えている」「空室が増える見込み」なら、将来的な収支悪化リスクも加味すべきです。
ポイント② 今後10年で必要な修繕は
⚫︎ 屋根・外壁・水回りなど大規模な修繕が近そう
⚫︎ 費用は手元資金でカバーできるか、借入が必要か
⚫︎ 修繕費用を賃料アップで回収できるか、空室率の改善につながるか
不動産は「持つなら、維持管理も責任をもつ」というのが基本となります。
費用はかかりますが、専門家による建物状況調査(インスペクション)を一度実施して、客観的に判断するのもおすすめです。
ポイント③ エリアの需要と空室リスク
⚫︎ 賃貸需要(学生、単身、ファミリーなど)があるエリアか
⚫︎ 築年数、間取り、設備などが競合物件と比べてどうか
⚫︎ 入居者のニーズに合わない場合、リフォームで対応可能か
地方や郊外では、「そもそも借り手が少ない」という状況もあるため、エリアの需給バランスを見誤らないことが重要です。
ポイント④ 管理・運営をどうするか
⚫︎ 自分でできるか、管理業者に委託するか
⚫︎ 委託する場合に、信頼できる会社は見つけられるか
⚫︎ 自分で対応する場合に、家族の協力は得られるか
持ち続けるなら、「大家」業は避けて通れません。
「手間をかけずに収益だけ得たい」という考えはトラブルになりがちなので、管理体制の確保は現実的に判断することが重要です。
ポイント⑤ 相続人の意見はまとまっているか
⚫︎ 相続で単独所有になるのか、共有所有になるのか
⚫︎ 共有になる場合、他の相続人はどう考えているか
⚫︎ 共有で持ち続ける場合に、管理などの「役割分担」や「収益分配」のルールは定めたか
相続で共有になる場合には、一人が主導的に動けて、他の相続人が協力的でないと、結局、何も決まらないまま放置されることが多くなります。
最初の段階で、しっかり話し合いを持つことが大切です。
ポイント⑥ 解体・建て替えは可能か
⚫︎ 再建築が可能かどうかを確認したか
⚫︎ 接道義務(原則、幅4m以上の道路に2m以上)は満たしているか
⚫︎ 解体費用や再建築コストの見通しはあるか
都市計画区域・防火地域・市街化調整区域など、土地にはさまざまな制約があることが多いので、そもそも建て替えができるのか、売却ができるのかなどの確認が必要となります。
これは「後で知って後悔する」ことにつながるので、必ず専門家に調査してもらうことをおすすめします。
ポイント⑦ ライフプランと合うか
⚫︎ 今後も賃貸経営を続ける意思はあるか、時間はあるか
⚫︎ その不動産を老後も持ち続けて安心か
⚫︎ 次世代(子や孫)は引き継ぎたいと考えているのか
どんなに収支が良くても、自分の人生プランに合っていなければ、持ち続けるのはストレスになります。
逆に、「自分も管理に関心がある」「将来子どもに資産として残したい」という場合は、長期的な運用も十分視野に入るでしょう。
判断は「感情」だけでも、「数字」だけでも難しいです。。
「数字で現実を見つめ」「感情で納得できる」判断をすることが、後悔しないカギになります。
【判断のための7つのポイント】
| ポイント | 内容 |
| 年間収支 | プラスかマイナスか |
| 修繕費の見通し | 今後、大規模修繕が必要か |
| 賃貸需要 | 空室リスクが高いか |
| 管理体制 | 自分または委託で管理できるか |
| 相続人の意思 | 意見はまとめっているか |
| 建て替え | 法的な制約はあるか |
| ライフプラン | 未来像に合っているか |
ケーススタディで学ぶ4つの選択
頭では「持つか売るか」「判断の視点」などを理解しても、実際の判断は簡単ではありません。
ここでは、よくある4つのケースをもとに、それぞれの選択がどのような結果を生んだのかをご紹介します。「自分だったらどうするか?」を考えるヒントにしてみてください。
【ケース1】売却で納得 兄妹で相続、早めの決断でスムーズに
50代の長女と次男が、都内にあった築45年のアパートを相続。
父親が亡くなり、アパート(6戸)には古くからの入居者が2世帯だけ。屋根や外壁は劣化し、給湯器も老朽化している状態でした。
最初は「修繕して賃貸を続けようか」という意見もありましたが、業者に見積もりを取ったところ、外装と設備改修で1,000万円超の費用が必要とのこと。
さらに、空室を埋めるには家賃を下げる必要があり、収支が合わないことがわかりました。
結果として、不動産業者に売却。立地の良さから思ったよりも高く売ることができました。
売却益は兄妹で均等に分け、「遺産で揉めることもなく、きれいに整理ができた」との声がありました。
【ケース2】管理会社と組んで、賃貸経営を継続
60代の男性が、地方都市にある築32年のアパート(8戸)を相続。
退職後に時間ができたため、「自分で大家をやってみよう」という気持ちで管理を引き継ぎました。
とはいえ、入居者対応やトラブルには自信がなかったため、地域で評判の良い管理会社と契約して運営を委託。
入居率がやや低かったので、一部の部屋をリノベーション。結果的に家賃アップに成功し、現在も安定経営を続けています。
「年金+家賃収入で老後が助かっている。修繕は預金なんとかカバーできている」とのことでした。
【ケース3】更地にして月極駐車場へ転用
郊外の築43年のアパートを相続した70代女性。
建物は雨漏りがあり、2年ほど空室状態で放置されていました。
不動産会社に相談したところ、「建物には買い手がつかないため、更地にしてからの売却、または活用を考えるべき」との助言を受け、建物を解体して月極駐車場に転用。
解体費用と駐車場の整備に200万円ほどかかりましたが、6台分の借り手がすぐに見つかり、年間約70万円の収入を確保しました。
「手間は少なく、税金も賃料収入でカバーできる。売ってしまわなくてよかった」とのことでした。
【ケース4】修繕にお金をかけすぎて、結果的に赤字
築40年、駅から徒歩15分の場所にあるアパート(6戸)を相続した40代男性。
当初、家賃収入が月20万円ほど入っていたため、「これならやれる」と判断し、全室リフォームに1,000万円超をかけました。
ところが、地域の人口減少や競合物件の増加により、思うように入居者が集まらず、3年経っても空室が半数以上という状況に。
しかも、リフォームローンを組んでいたため、毎月の返済に追われ、ついには赤字が続いて売却を検討することになってしまいました。
「立地や需要をよく調べてから判断すべきだった」と後悔されていました。
どのケースにも共通しているのは、「冷静な現状把握」と「慎重な判断」が鍵だったことです。
自分ひとりで抱え込まず、専門家や管理会社の助言を受けながら方向性を決めた人は、後悔が少ないように感じます。
専門家を「使いこなす」ためのヒント
老朽アパートの相続は、「不動産」「税金」「法律」「建物管理」など、複数の領域が絡み合う複雑なテーマです。
すべてを自分一人で判断しようとせず、信頼できる専門家のサポートを上手に使うことが、後悔しない選択への近道です。
ここでは、どのような内容を、どの専門家に相談すべきかをご紹介します。
不動産会社(売却・賃貸管理)
⚫︎ 売却価格の相場、賃貸需要、修繕の必要性などをチェック
⚫︎ 管理委託を考えるなら、管理費の内訳や対応範囲などをしっかり確認
税理士(相続税・譲渡所得税)
⚫︎ 相続税の試算、申告(さまざまな特例の適用可否などをチェック)
⚫︎ 売却時の譲渡所得税の試算
⚫︎ 修繕費や解体費の会計上の処理方法
税理士には得意分野、専門分野があります。相続や不動産に強い税理士を選ぶことが大切です。
建築士・インスペクター(建物の診断)
⚫︎ 建物の構造や設備の劣化状況を第三者の立場で診断
⚫︎ 修繕の優先順位や概算費用の提示
将来的に建て替えやリフォームを検討している場合は、特に有効となります。
不動産相続のコンサルタント(総合的な判断)
⚫︎ 所有、売却、再投資など、ライフプラン全体を見据えた総合的な判断をサポート
⚫︎ 相続人の間の意見調整や、協議の取りまとめも
「選択肢を広げたい」「今後の不動産運用も含めて総合的に考えたい」といった時に、とくに力を発揮します。
上手な相談のポイント
⚫︎ 困ってからではなく、「どうしようか」と考え始めた段階で早めに相談するのがおすすめです。
⚫︎ 物件資料(登記簿、図面、収支データなど)を揃えておくとスムーズです。
⚫︎ 総合的な窓口(ワンストップ)にまずは相談し、必要な段階で専門の士業に連携してもらうのがうまくすすめるコツです。
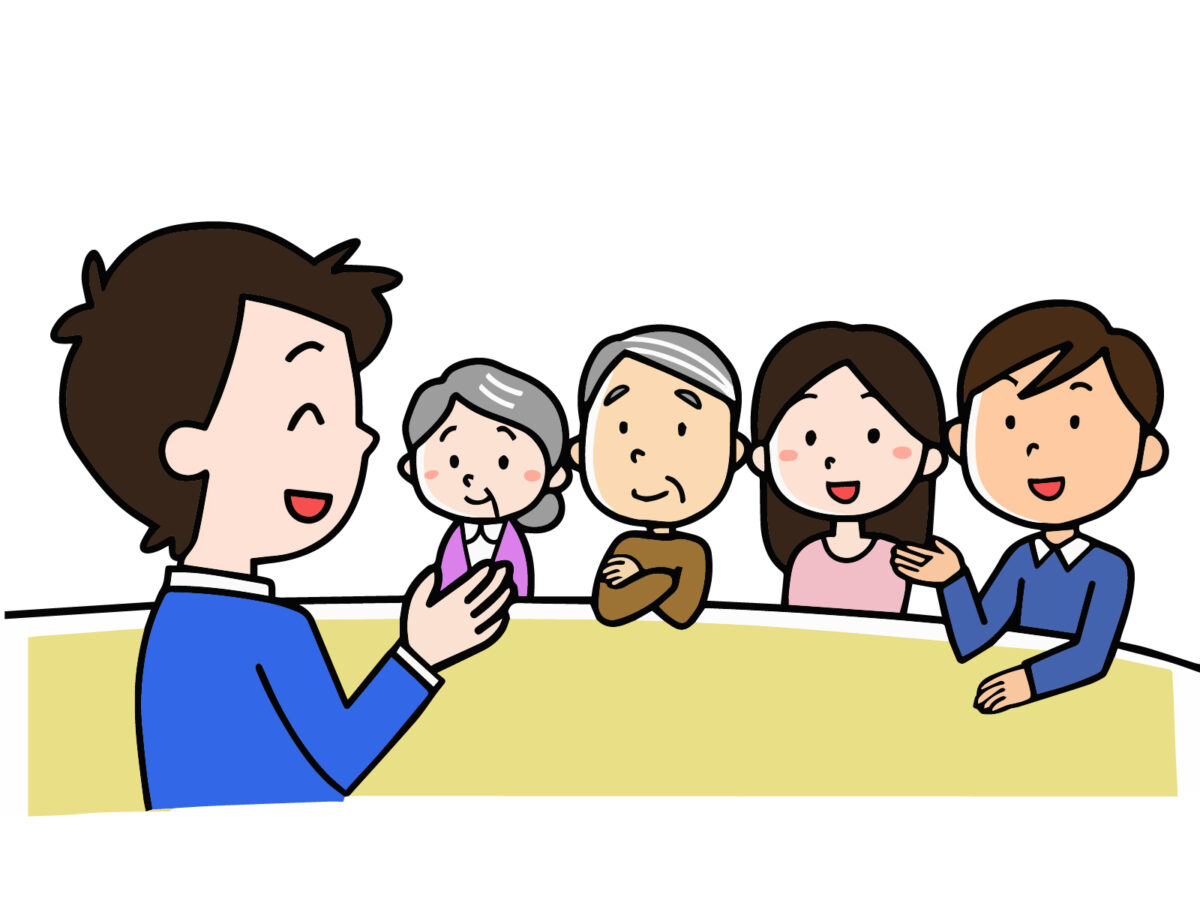
まとめ
老朽アパートを相続すると、収益物件という面と、老朽資産という面が混在しているため、判断がとても難しくなります。
持ち続ける・売却する・建て替える・更地にする・プロに任せる、などなど。
選択肢は思った以上に多く、正解は一つではありません。
あなたにとっての「最適解」はどこにあるか
判断を誤って「修繕費だけが膨らみ赤字に…」「売り時を逃して、価値が下がってしまった…」
そんな後悔をしないためにも、以下の3つを大切にしてください。
✔️1. まず現状を「見える化」する
⚫︎ 建物の状態(修繕履歴、劣化状況など)
⚫︎ 家賃収入と支出
⚫︎ 周辺エリアの賃貸需要
✔️2. 「持ちたい資産か」を考える
⚫︎ 自分で管理できるか(管理会社への委託を含む)
⚫︎ 次世代(子や孫)に引き継ぐ意思はあるか
✔️3. 必要なときに、誰かに相談する
⚫︎ 専門家への相談は「リスク回避」の一手
⚫︎ 「悩んでいる時間」が、不動産の価値の目減りにつながることも
相続は、家族の思いとお金の現実が交差するタイミングです。
だからこそ、感情に流されすぎず、かといって数字だけで切り捨てず、自分らしい「納得のいく判断」をすることが大切です。
「うちのアパート、どうしたらいい?」
そんなときは、いつでもお気軽にヴェルダントにご相談ください。
お悩みを整理するところから、一緒に考えてまいります。


