二拠点居住で知っておきたい相続の注意点

テレワークの普及やライフスタイルの多様化を背景に、「二拠点居住」という言葉を耳にする機会が増えました。
平日は都市部で暮らし、週末や休暇は地方の古民家やリゾート地の別荘に滞在する。あるいは、親から相続した実家をセカンドハウスとして利用する。そんな暮らし方が「新しい豊かさ」として注目されています。
国土交通省は2023年11月に二地域居住の推進に関する調査を公表し、二拠点居住を政策的にも後押ししています。背景には人口減少や空き家の増加といった社会課題もあります。実際、総務省「住宅・土地統計調査(2023年)」によれば、日本の空き家は900万戸、空き家率13.8% に達しており、放置空き家の活用が大きなテーマとなっています。二拠点居住は、その有効な活用策のひとつでもあるのです。
→国土交通省「二地域居住等の最新動向について」
しかし、二拠点居住が魅力的である一方、いざ相続の場面になると意外な「落とし穴」が潜んでいます。誰がどちらの家を引き継ぐのか、固定資産税や管理費用をどう分担するのか、税制上の扱いはどうなるのか。トラブルになりやすいポイントを知らないまま二拠点居住を続けていると、将来相続人が困ることになりかねません。
本記事では、二拠点居住と相続にまつわる注意点を、典型的な事例などを交えながらわかりやすく解説します。

二拠点居住と空き家活用の接点
二拠点居住の実践には大きく2つのパターンがあります。
- 都市部の自宅+地方の別荘やリゾート地の拠点
- 都市部の自宅+親の実家(相続した不動産)
後者は相続や終活と直結しているため、特に注意が必要です。
国交省の調査でも、二地域居住の候補として「相続した実家や空き家を使いたい」という声が多く挙げられています。しかし、利用頻度が低ければ固定資産税や修繕費の負担は重く、所有者が亡くなったときには相続人の間で「使いたい派」と「売りたい派」が対立することもあります。
つまり、二拠点居住と相続は切っても切れない関係にあるのです。
相続で注意すべき4つのポイント
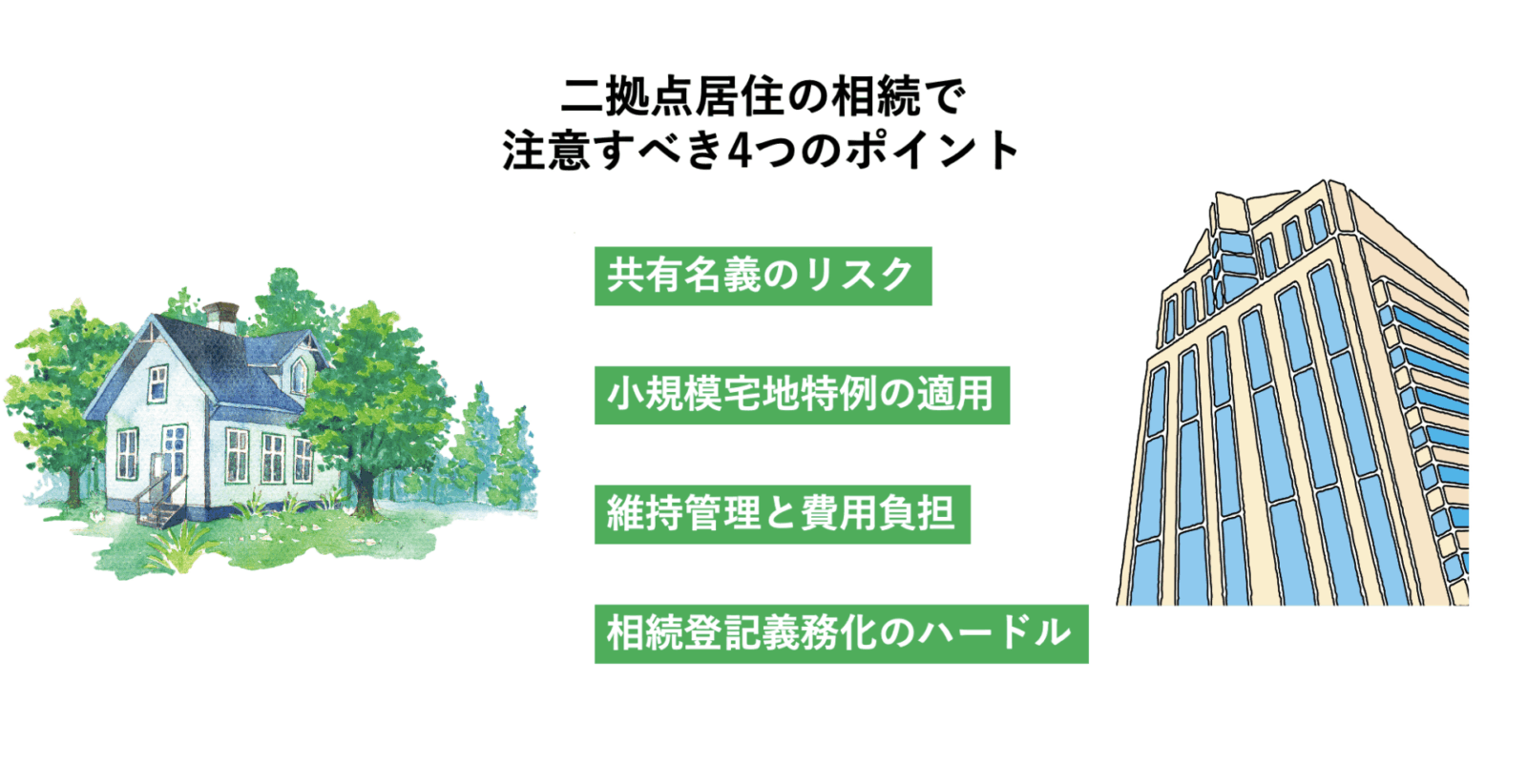
1. 共有名義のリスク
二拠点居住の相続で最も問題になりやすいのが「共有名義」です。
たとえば、親が亡くなり、都会のマンションと地方の実家を子ども3人で共有で相続した場合を想像してみましょう。
- 長男:都会のマンションを重視、実家は売りたい
- 次男:実家をセカンドハウスとして残したい
- 長女:どちらも売却して現金化したい
このように利害が分かれると、簡単には合意できません。共有名義の不動産は売却・賃貸・解体などの重要な決定に相続人全員の同意が必要となります。1人でも反対すれば手続きは進まず、結果として「誰も使わない空き家」が残ってしまうことも珍しくありません。
典型的なケース
相続から数年が経過しても売却も賃貸もできず、固定資産税の支払いと管理コストだけが積み上がる。空き家は荒れていき、近隣から苦情が出て初めて動き出すことに。。
2. 小規模宅地等の特例の適用
相続税対策で大きな効果を持つのが「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例は、被相続人(亡くなった人)が居住していた宅地を相続した場合、最大330㎡まで土地の評価額を80%減額できる制度です。相続税の算出で、税負担の軽減に大きく役立つことになります。
しかし二拠点居住の場合、「どちらを居住用宅地とみなすか」が問題になります。
たとえば、親が平日は都心のマンション、週末は郊外の戸建てで暮らしていたとします。郊外の戸建て用宅地で小規模宅地等の特例の適用を受けたいところですが、どちらを主たる居住と認めるかは、住民票の所在地や生活実態で判断されます。主たる居住が証明できないと税務署に小規模宅地等の特例が認められない可能性があります。
典型的なケース
親が二拠点で生活していたが、住民票は都会に置いたまま。相続後、郊外の家を「居住用」と主張しても認められず、相続税が数百万円増えてしまう結果になった。
3. 維持管理と費用負担
二拠点居住は豊かな暮らしの象徴である反面、維持費用は二倍です。
相続後、空き家となった場合には費用の押し付け合いで相続人間に亀裂が生じかねません。
具体的には、
- 固定資産税
- 水道光熱費の基本料金
- 草刈りや雪下ろし、屋根・外壁修繕等の費用
こうした負担を誰が引き受けるのか。遠方の相続人にとっては「行かない家にお金を払うなんて不公平」と感じやすく、争いの火種となります。
典型的なケース
兄弟3人で実家を相続。長男は近隣に住んで管理を引き受けているが、次男と三男は遠方在住。結局、長男がほとんどの費用を負担し不満が爆発。兄弟の仲が悪化してしまった。
4. 相続登記義務化のハードル
2024年4月から施行された「相続登記の義務化」により、相続発生から3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料に処される可能性があります。
二拠点居住の家も対象であり、名義を整理しなければ売却や賃貸に進めません。相続人が全国に散らばっている場合、書類のやりとりに時間がかかり、期限を過ぎてしまうケースも想定されます。
典型的なケース
親が亡くなった後、実家の名義変更を後回しにして数年放置。いざ売却しようとしたときに「まず相続登記を」と言われ、相続人が集まらずに売却時期を逃した。
二拠点居住と相続 ― トラブルを防ぐために
生前から方針を決めておく
「どちらの家を誰に相続させるか」を親世代のうちに遺言で明確にしておくと、後々の争いを防げます。特に二拠点居住の場合は曖昧にせず、主たる居住用宅地を指定しておくことが重要です。
専門家に相談する
相続税や登記の実務は専門性が高く、個人だけで判断するのは危険です。税理士や司法書士、不動産コンサルタントに相談すれば、制度の落とし穴を避けられます。
選択肢を知っておく
二拠点の家を「残す」以外にも、「貸す」「売る」「シェアする」「引き取ってもらう」といった出口戦略があります。民間の新しいビジネスモデル(マッチングサイトや有料引き取りサービス)を知ることで、より現実的な判断ができます。
まとめ
二拠点居住は人生を豊かにしてくれるライフスタイルですが、相続の場面では思わぬリスクがあります。
- 共有名義で合意が取れない
- 小規模宅地等の特例が使えない
- 維持費の負担が不公平を生む
- 相続登記義務化で手続きが遅れる
こうした落とし穴を避けるには、「生前から相続を意識すること」が不可欠です。
国交省などのデータが示す通り、二拠点居住は広がりを見せています。だからこそ、今のうちに「二拠点の家をどう相続するか」を家族で話し合い、専門家に相談しておくことが大切です。
安心して二拠点居住を楽しみ、相続の際にも家族が揉めないように、早めの準備が、豊かな暮らしを未来につなぐカギになります。



