なぜ相続争いをすると相続税が高くなるのか?
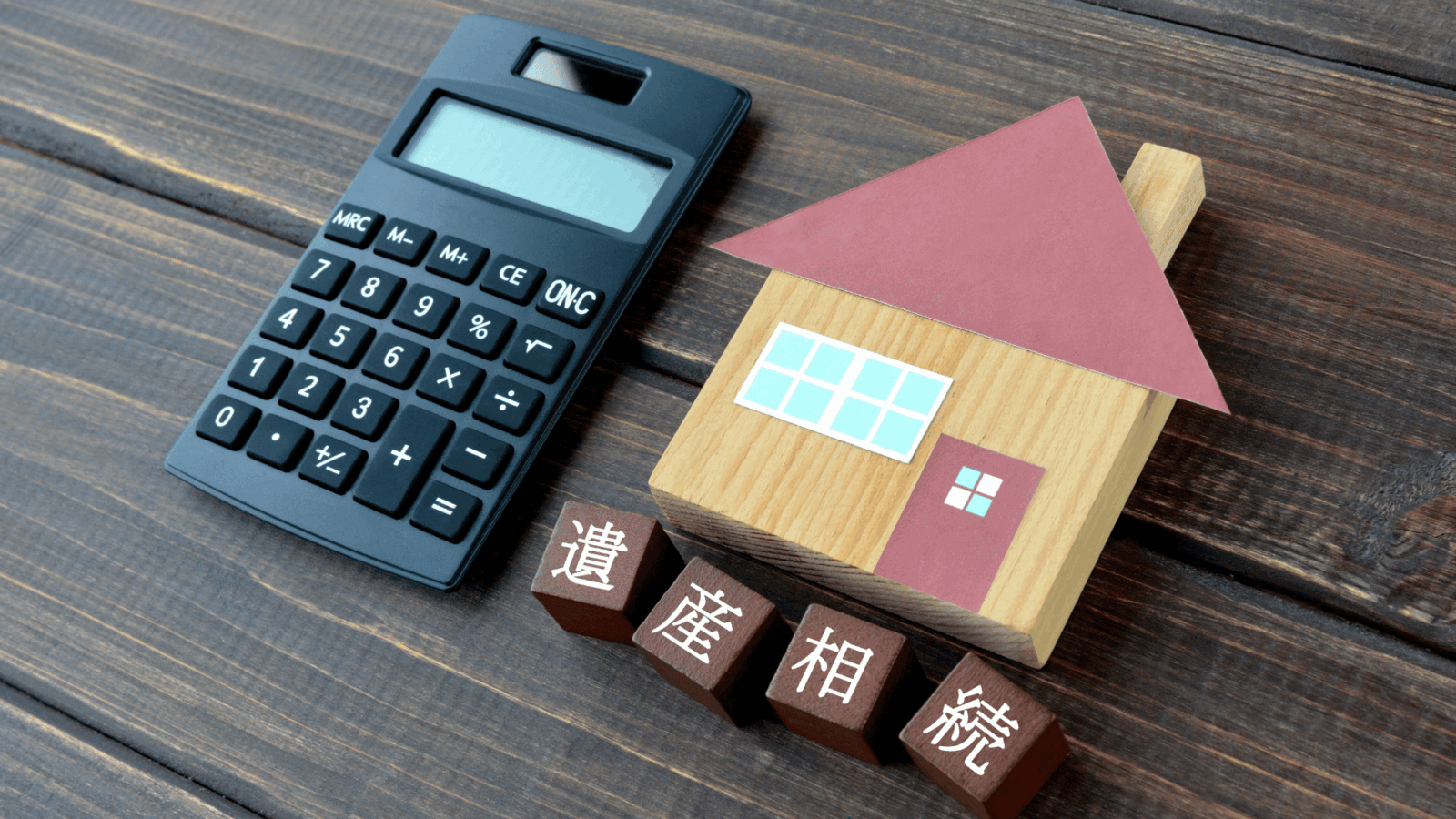
1. 相続争いが招く“税金の落とし穴”
「争族」という言葉を最近よく耳にするようになりました。
相続をめぐって親族間で争いが起きることを、皮肉を込めてこう呼びます。いわゆる「遺産争い」「相続争い」のことです。兄弟や親戚の関係が壊れてしまう。。そうした悲しい事態を指すのですが、実は「争族」が招くのは心の傷だけではありません。税金の面でも大きな不利益が生じることがあるのです。
相続税には「相続開始から10ヵ月以内に申告・納付しなければならない」という期限があります。この期限までに遺産分割協議がまとまらなければ、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった強力な節税の制度が使えなくなり、本来よりも高額な相続税をいったん納める事態となってしまいます。
相続争いの代償は「仲が悪くなるだけ」ではありません。“お金と時間の損”にもつながるのです。だからこそ、早めに家族で準備を進め、必要に応じて専門家にご相談いただくことが大切です。

2. 相続税には10ヵ月のタイムリミットがある
相続税の申告・納付期限は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内です。
この10ヵ月は、実際に手続きを進めてみると驚くほど短い期間です。葬儀や法要などで慌ただしい日々を送りながら、被相続人の財産の調査や評価、相続人同士の話し合いを同時に進めなければなりません。
特に重要なことが「遺産分割協議」です。相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを合意し、書面(遺産分割協議書)にまとめ、全員が署名押印しなければなりません。
分割がまとまらない場合の影響
10ヵ月の期限までに分割が成立しなければ、相続税の申告は「未分割」のまま行うしかありません。この場合、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などが一切使えず、控除なしの高額な相続税をいったん納める必要があります。
実務上の問題点
✔️ 多額の現金が必要:相続税は原則、現金一括納付です。場合によっては数千万円単位の現金が必要となります。
✔️ 資金繰りが重荷に:この段階で相続財産の不動産を売却することはできません。まだ誰が相続するか確定していないからです。そのため、相続人自身がもともと所有している不動産を売却したり、金融機関から借入をしたりして、納税資金を確保するケースもあります。
✔️ 手続きの煩雑化:後日、遺産分割がまとまったら、払いすぎた相続税を還付してもらうため「更正の請求」をする必要があります。控除を適用し直す作業となるので、二度手間になります。一方でもし、3年以内に遺産分割がまとまらなければ、結局、控除は適用されず、高額なままの相続税が確定することになります。
つまり、相続争いは「心理的ストレス」だけでなく、「資金繰りや手続きの負担」にも直結してしまうのです。
→関連コラム「相続で覚えておきたい数字『3、4、10』」
3. 控除や特例が使えないとどうなるのか
(1) 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
相続税に関して最も強力な控除の制度が「配偶者の税額軽減」です。
配偶者が取得する相続財産については、1億6,000万円か、または法定相続分相当額のどちらか大きな金額まで非課税になります。
通常、配偶者が相続すると相続税がゼロになるケースが多いのはこの制度があるからです。
しかし、遺産分割が確定しなければ「配偶者がどれだけの財産を相続するのか」が決まらないため、この控除は使えません。結果として、本来ならゼロで済むはずの相続税が数百万円〜数千万円かかってしまうこともあるのです。
(2) 小規模宅地等の特例
もうひとつ大きな控除となるのが「小規模宅地等の特例」です。
自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たせば相続税の評価額を最大80%減額できる制度です。
たとえば5,000万円の土地が1,000万円として評価されるので、課税額は大幅に減ります。
しかし、これも「誰がその土地を相続するのか」が決まらないと適用できません。未分割のままでは、この特例が使えず、土地の評価額は満額で計算されることになります。
(3) その他の控除にも影響
さらに、次のような制度も「遺産分割が成立していること」が適用の条件となります。
⚫︎ 相次相続控除:前の相続から10年以内に再び相続が発生した場合、二重課税を緩和する制度
⚫︎ 未成年者控除:未成年の相続人に対し、成人までの年数×10万円を控除
⚫︎ 障害者控除:障害者の相続人に対し、85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)を控除
いずれも「誰がどの財産を受け取るか」が確定しないと控除額を計算できません。
4. 救済措置「申告期限後3年以内の分割見込書」
遺産分割がまとまらなくても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば救済されます。いったん特例なしで申告・納付した後、3年以内に分割が成立すれば、更正の請求で控除を適用し、払いすぎた税金を還付してもらえます。
プラス3年の猶予期間を得ることができるわけです。
ただし注意点も
✔️ 3年を過ぎるとアウト:結局、控除は適用できず、高額なまま相続税が確定
✔️ 資金繰りの負担:分割がまとまるまで払いすぎた税金は戻らないので、資金繰りの負担は重いまま
✔️ 手続きが複雑化:更正の請求をするための追加手続きが必要になる
つまり「分割見込書」は時間を稼げるだけで、根本的な解決にはなりません。

5.具体例で見る「争族」の代償
事例
相続財産:自宅5,000万円+預金2,000万円
相続人:妻と子2人
基礎控除
相続税には「基礎控除」があり、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」 で計算されます。
この場合、相続人は計3人なので、基礎控除額は 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。
遺産分割がまとまる場合
妻が自宅(5,000万円)と預金(1,000万円)を相続、子2人が預金(残り1,000万円)を相続したとする
妻が相続した自宅(5,000万円) → 「小規模宅地等の特例」で評価額1,000万円
妻が相続した預金(1,000万円) → 「配偶者控除」で非課税
課税される相続財産:1,000万円+1,000万円(子2人が相続した預金)=2,000万円
基礎控除4,800万円以下 → 相続税はゼロ
争族となり遺産分割がまとまらない場合
「配偶者控除」も「小規模宅地等の特例」も適用できない
課税される相続財産:5,000万円(自宅)+2,000万円(預金)=7,000万円
基礎控除4,800万円を差し引いて →2,200万円に課税 →相続税は計225万円
遺産分割がまとまっていれば相続税が発生しなかったはずが、協議がまとまっていないと、225万円をいったん現金で納付することになってしまうのです。さらに後日、「更正の請求」の手続きをしないと、還付もされないということになります。
この事例は比較的コンパクトな遺産規模のため数百万円に留まりますが、遺産が数億円規模になると、いったん納める相続税額は数千万円規模となってしまいます。
| 遺産分割協議 | 適用控除 | 課税財産額 | 相続税額 |
| まとまる | 配偶者控除 小規模宅地特例 | 2,000万円 | なし |
| まとまらない | なし | 7,000万円 | 225万円 |
6. 「争族」を防ぐことが最大の節税
ここまで見てきたように、「争族」=相続争いは、心理的ストレスにとどまらず、税金・資金繰り・手続きの三重苦を招きます。
だからこそ、最も重要なのは 「争族を未然に防ぐこと」となります。
そのためには次のような備えが大切です。
⚫︎ 適正な遺言書(できれば公正証書遺言)を作成する
⚫︎ 生前贈与で財産を早めに整理しておく
⚫︎ 家族信託を活用する
⚫︎ 相続人同士で事前に情報を共有しておく
こうした備えをしておくことが、相続税の控除や特例をフルに活用することにもつながり、余計な負担を避けられる可能性が高まります。
7. まとめ
相続争いが長引くと、配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えず、本来ならゼロだった相続税が数百万円〜数千万円に跳ね上がることもあります。
救済策はあるものの、いったん多額の税金を納めなければならず、資金繰りや手続きの面で大きな負担が生じます。
「争族を防ぐことこそ、最大の節税策」
そのためには、早めの備えと専門家への相談が欠かせません。家族の未来を守るために、いまから一歩を踏み出しましょう。



