「この家を次男に譲りたい」 不動産の分割贈与とは
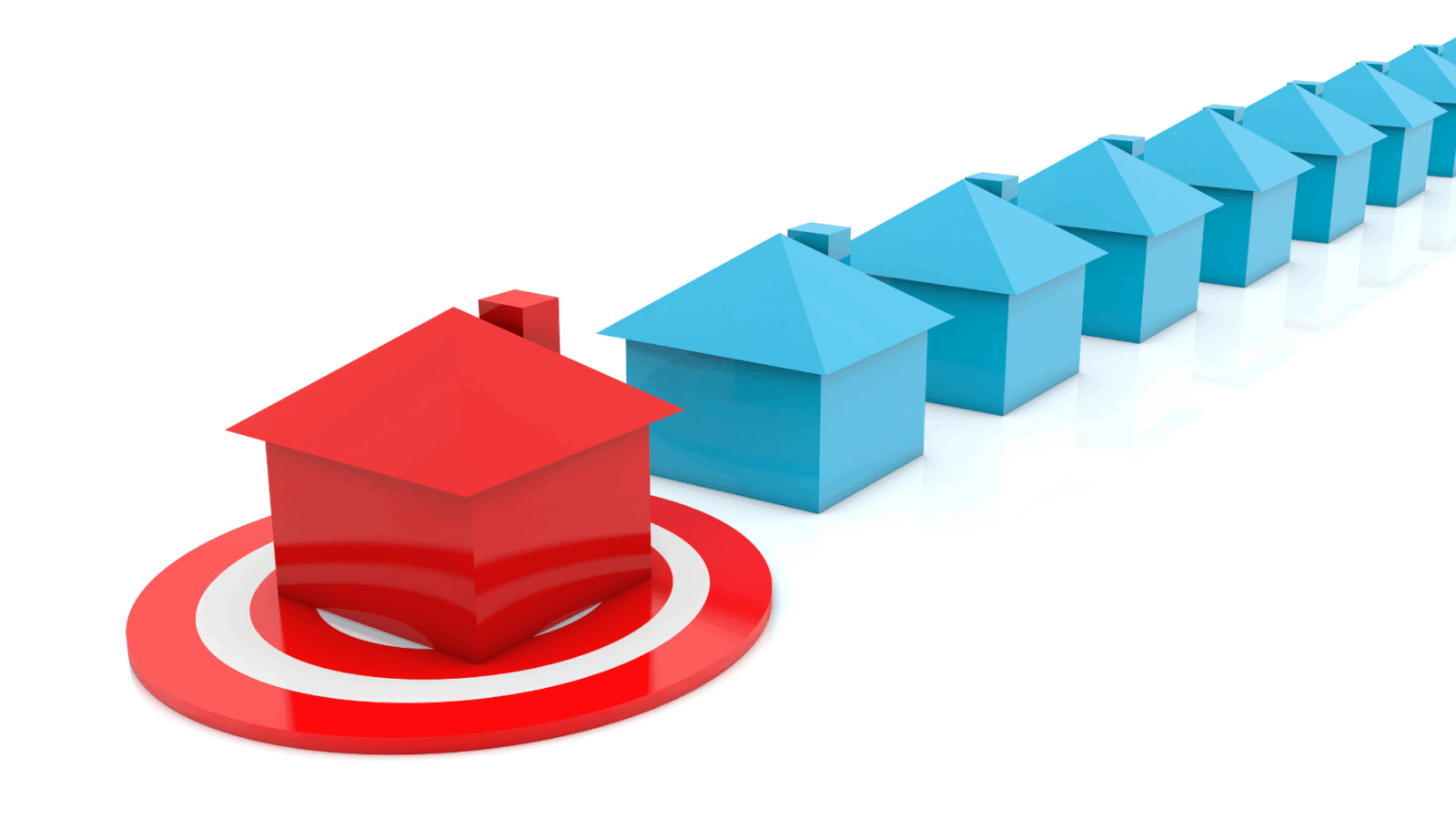
「この家は、どうしても次男に譲りたいんです」
不動産の相続で、こうしたご相談は少なくありません。
親と同居していた、介護してくれた、ずっと世話をしてくれたなど。
そうした思いがこもった家族に、ご自宅などの不動産を譲りたいことがあります。
ですが、不動産を丸ごと譲るのは、他にも相続人がいる場合には、分け方や税金など超えなければならないハードルがいくつかあります。
そんなときに確実に特定の家族に譲る方法として検討されるのが生前贈与です。
ただ、気になるのは贈与税などの負担です。
今回のコラムでは、「不動産の権利を分割して数年かけて贈与する」という方法に焦点をあてます。
贈与税の負担を減らすことはできるのか、メリットや注意点についてわかりやすく解説します。

不動産の「分割贈与」とは?
不動産の権利を分割して贈与するとは、家や土地を物理的に分けるのではなく、所有権の権利を分けた「持分」を贈与する方法です。
たとえば、自宅の土地建物の持分を5分の1ずつ5年かけて、あるいは10分の1ずつ10年かけて子に贈与していくといった方法です。
この方法であれば、毎年の暦年贈与の非課税枠(110万円)を活用して、贈与税の負担を抑えながら、最終的には子どもが全ての権利を取得することが可能になります。
相続を待たずに、「譲りたい人」に不動産を引き継げることが、大きな魅力です。
分割して贈与するメリット
1. 譲りたい家族に確実に渡せる
相続では、法定相続人は法律に定められた相続分を持つことになります。
そのため「この家は次男に」という親の意思があっても、不動産を相続する際に、長男や他の相続人との共有になってしまう可能性があります。
生前に贈与しておくことで、特定の家族に優先的に譲ることができ、相続の時点ではその家族が所有権を持っていることで、他の相続人との共有になることを防ぐことにつながります。
2. 暦年課税の非課税枠を活用できる
暦年課税制度では、年間110万円までの贈与であれば、贈与税が非課税となります。
不動産は大きな資産なので、非課税枠の110万円以内の持分の贈与は難しいかもしれませんが、それでも毎年少しずつ不動産の持分を贈与することで、この非課税枠を活用できます。
相続時にまとめて相続税の評価をされるよりも、贈与税の非課税枠を活用して段階的に贈与しておいた方が、全体の税負担を抑えられる可能性があります。
ただし贈与ごとに贈与契約を結ぶなど、一体としての「連年贈与」などとみなされないように注意が必要です。
3. 不動産価格の上昇前に持分を贈与できる
不動産価格が今後上がると予測される場合は、価格が上昇する前に一部だけでも贈与しておくことで、その後の相続時に評価額が上がり相続税の負担が増えてしまうというリスクを軽減することができます。
ただし、不動産価格が実際にどうなるかを予測するのは非常に困難ですし、想定よりも上昇幅が小さくて税負担を減らす効果が結果としてあまりなかったということも考えられるので、注意が必要です。
4. 家族の意思確認の第一歩に
贈与は「相続の準備」を進めるうえでも有効です。
誰が何を引き継ぐのかを事前に整理し、それを生前贈与という形で示すことで、家族間の認識の共有や合意形成につなげることができます。
それが結果として、相続後のトラブルを防ぐことにつながる可能性があります。
分割贈与の注意点とデメリット
一方で、分割贈与には注意すべき点がたくさんあります。
1. 登記料や諸費用が毎回かかる
不動産の贈与で所有者が変更になると、登記料(登録免許税)や司法書士報酬が発生します。さらに贈与税の処理のために税理士報酬が発生する可能性もあります。
贈与の回数が増えるほど、手間とコストがかさみむことになります。
これらの費用を合わせると1回で10数万円程度となるので、数回に分けて贈与した場合は、諸費用が数十万になることもあります。
2. 相続前7年以内の贈与は持ち戻される
2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続税の計算の対象とされることになりました。
これを「持ち戻し」といいます。
(改正前は3年以内の贈与が対象だったが、持ち戻しは段階的に延長され、7年以内となるのは2031年から)
数回に分けて贈与していても、亡くなる直前数年分の贈与は、結局相続税の計算に加算されてしまうことになります。
節税だけを目的とする分割贈与は、加算期間の延長でリスクが高まったと言えます。
→国税庁「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」(2024年1月1日施行)
3. 相続時精算課税制度は使いづらい
上記のような1年ごとに贈与税を処理する「暦年課税制度」とは別に、「相続時精算課税制度」があります。
「相続時精算課税制度」を選択すると、年ごとの基礎控除額110万円に加えて累計の特別控除額2,500万円まで贈与税が非課税になります。
一見、優位に見えますが、基礎控除額を超えた分は結局、相続時に相続税の計算に加算されてしまうので、相続税が発生する遺産が予想される場合は、あまり効果がありません。
さらに、一度、「相続時精算課税制度」を選択してしまうと、同じ人からの贈与では暦年贈与が使えなくなってしまいます。
4. 小規模宅地の特例が使えなくなる
相続時に相続税の負担を軽減する効果が大きい「小規模宅地等の特例」が、生前贈与された土地については、相続時に使えなくなります。
小規模宅地等の特例は、亡くなった人(被相続人)の自宅や事業用地の評価額を最大80%減額できる制度です。
相続時に贈与した不動産が持ち戻された場合に、この大きく評価額を減らせる制度が利用できず、贈与時の評価額のまま相続税の計算がされるということになり、結果的に納税額が大きくなってしまうこともあります。
小規模宅地等の特例を利用する条件は細かく定められていますが、生前贈与しようとしている土地がこの特例の適用条件に合っている場合は、より詳細なシミュレーションをして判断することが大切です。
5. 家族間の共有はトラブルのもと
不動産の持分を贈与すると、その不動産を共有している状態となります。
共有状態となると、売却・リフォーム・賃貸などの判断をする際に、共有者全員の同意が必要になります。
たとえば、親と子の共有状態となっている時に、仲が悪くなり、親がやはりその不動産を売ってしまおうとしても、子が反対すると売却できないということになります。
また、親の持分が残ったまま相続が発生すると、親の持分が相続対象となるので、他の相続人とのトラブルにつながってしまう可能性もあります。

まとめ
不動産を「誰にどう残すか」は、税金だけでなく家族関係にも大きな影響を与えます。
分割して生前贈与するという方法は、「譲りたい人に確実に渡したい」という思いを叶える有効な手段です。
ただし一方で、制度の複雑さやリスク・デメリットも多いといえます。特に税に関することは税理士など専門家に相談し、さまざまなポイントを考慮して総合的に判断することがとても重要です。
「譲りたい人に渡したい」という意思を明らかにするには、「遺言書」が確実といえるので、法的に有効な「遺言書」の作成をまずは検討するのがよいと思います。
節税だけでなく、家族にとっても良いかたちを目指して、早めに準備を始めましょう。


